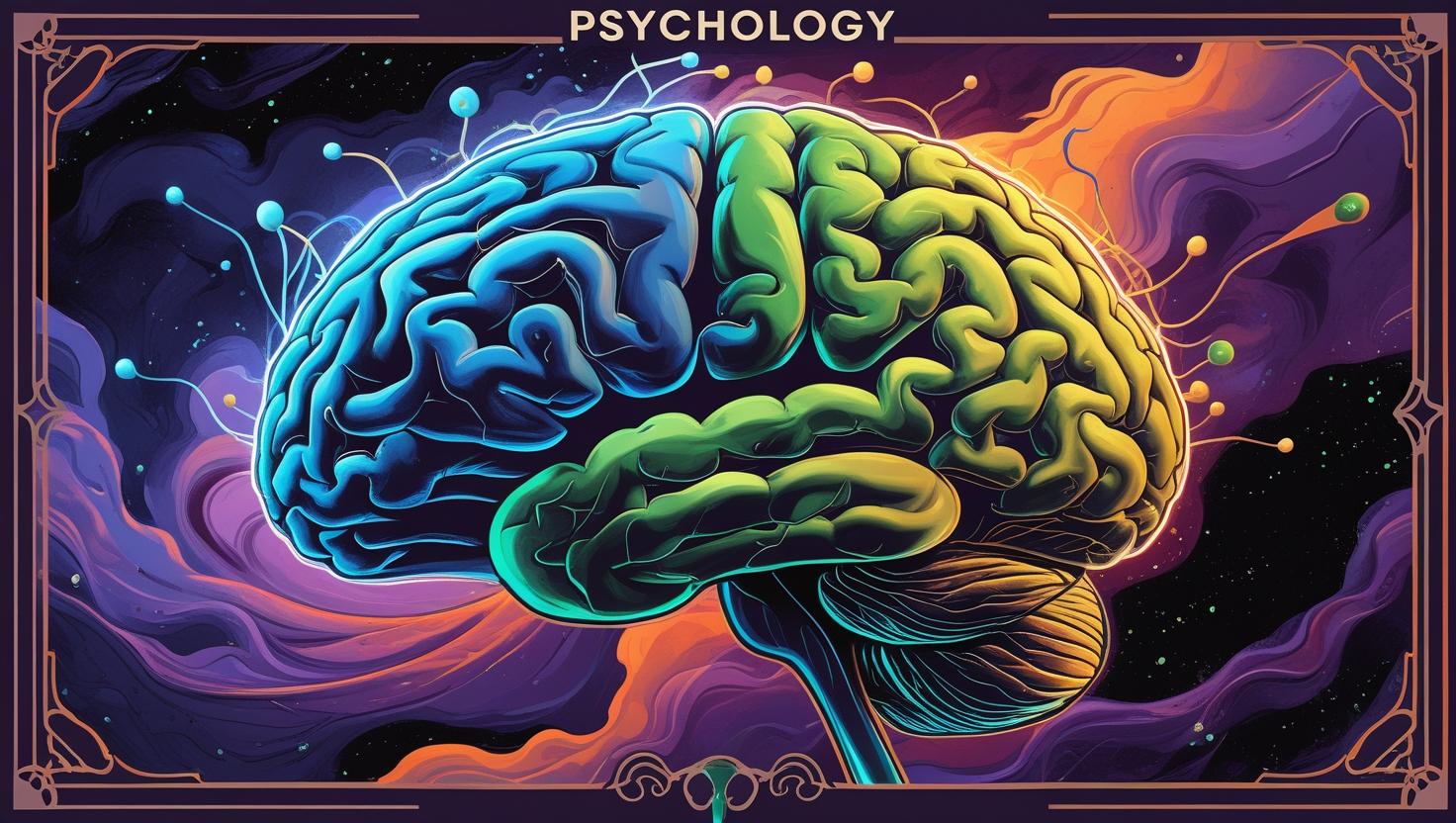こんにちは、カカポです!
「心理学って面白そう!」「難しすぎない心理学ネタを知りたい!」「日常生活で使いたい!」
↑この記事では、こういった方の悩みを解決していきます。
「心理学が何なのかわからない…」という方はこちらの記事をどうぞ↓
関連記事: 心理学ってなに?
日常生活で使える!面白い心理学ネタ10選!
実は心理学って、私たちの毎日の会話やSNSのやりとり、買い物するとき、恋愛など、あらゆる場面にかかわっているんです!
そして、ちょっと笑える・ドキッとする「面白い法則」や「心のクセ」も盛りだくさんです!
ではさっそく、「思わず誰かに話したくなる」心理学のトリビアや効果を紹介していきます。
1,ゲインロス効果
「ゲインロス効果」とは、最初は冷たかった人が急に優しくなると、より強く惹かれてしまう。という効果です。
なぜ、「最初から優しい人」より「最初は冷たかったけど、急に優しくなった人」に強く惹かれてしまうのかというと、人は「感情の落差」が大きいほど印象に残るからです。
つまり、ずっと優しい人より「最初だけちょっと不愛想だった人」の方が後々好感度が上がりやすいんです!
2,バーナム効果
「あなたは繊細だけど、時々大胆な一面もあります」
こんなことを言われて「うわ、当たってる!」と、思ったことはありませんか?
この心理現象は、「バーナム効果」といいます。
誰にでも当てはまるような曖昧な言い回しを、自分だけの特徴だと感じてしまうのです。
占いや、性格診断を過剰に信じてしまうのはこの心理現象が働いているからなんです!
3,ミラーリング効果
自分の話し方、しぐさ、価値観が似ている人になんとなく好意を抱いたことはありませんか?
この現象は「ミラーリング効果」といい、人は自分に似た人に好意を持ちやすいという性質があるからなんです!
仕事、恋愛、学校でも、この心理効果は利用できます。
さりげなく相手の言動をマネると、相手との距離がぐっと縮まります!
相手をよく観察し、真似しやすそうなしぐさや言動を見つけ、ぜひ「ミラーリング効果」を実際に使ってみてください!
4,ザイオンス効果
「最初は好きでも嫌いでもなかったのに、顔を合わせる回数が増え始めると気になってしまう…」
なんていう経験はありませんか?実は、この現象には心理学的にちゃんと理由があるんです。
「ザイオンス効果(単純接触効果)」と言って、人は接触する回数が多いほど相手に親しみを感じるのです。
SNSを使用している際に、繰り返し広告が表示されたことはありませんか?
その理由は、広告を表示する人が「ザイオンス効果」が働くことを狙っているからなんです!
5,ハロー効果
テレビで活躍する俳優の人、日常生活で顔のかっこいい人を見かけたとき、
「この人、顔もかっこいいし絶対性格もいいはず!」と思ったことはありませんか?
その現象には名前がついており、「ハロー効果」といいます。
1つの目立つ特徴(外見・地位など)が、他の評価にまで影響を与えてしまう現象のことを言います。
よく「見た目が9割」という人がいるのも、この効果が理由です!
6,プライミング効果
「老人」という単語を何度か見せられた人は、その後の歩くスピードが遅くなった。
↑これは、1996年、心理学者「ジョン・バージ」らが行った有名な実験です。
実験内容:
- まず、被験者に「文章を並べ替えて文を作るタスク」をさせます。
- Aグループには「老人」関連の単語(例:しわ、杖、白髪、ゆっくり)を含む文を出題。
- Bグループには、そうした単語が入っていない普通の文を出題。
- その後、部屋を出て廊下を歩いて帰る様子を観察。
実験結果:
なんと、老人の単語を見たグループ(Aグループ)の方が、歩くスピードが遅くなっていたのです。
つまり、無意識に「老人」というイメージに影響され、歩くスピードまで変化したということです。
これは「プライミング効果」と言って、先に見たり聞いたりした情報がその後の行動や判断に影響するという効果です!
7,カクテルパーティー効果
居酒屋、学校、などの騒がしい場所でも自分の名前だけははっきり聞こえた経験、ありませんか?
その現象を「カクテルパーティー効果」と言って、脳が重要な情報だけを選んで処理している証拠です!
「カクテルパーティー効果」に関する代表的な実験を一つ紹介します。
1953年、この効果を最初に実験的に示したのは、イギリスの心理学者「コリン・チェリ」です。
実験の内容:ダイコティック・リスニング(両耳分離聴)
- 被験者にヘッドホンをつけ、左右の耳に異なる音声(会話など)を同時に流す。
- 右耳にはニュース、左耳には別の会話など。
- 被験者には「右耳の内容に集中してください」と指示。
- 後で、左耳(=無視する側)の内容をどれだけ覚えていたかを確認。
結果:
- 無視した側の会話の内容そのものはほとんど覚えていませんでした。
- しかし、自分の名前や特定のキーワードが出ると、それに反応してしまうケースがあったのです。
要するに私たちの脳は、意識しなくても「大切な情報」をしっかり選んでくれているんです!
8,ピグマリオン効果
「ピグマリオン効果」とは簡単に言えば、期待されると実際に成績が伸びやすくなるという効果です。
他人からのポジティブな期待が、その人の行動、能力を実際に高めてしまうのです。
代表的な実験を一つ紹介します!
実験内容:・ローゼンタールとジャコブソンの実験(1968)
- まず、小学校の先生に「知能指数が今後大きく伸びる可能性がある児童のリスト」を渡します。
- ただし、このリストは本当の知能検査ではなく、ランダムに選んだ児童の名前です。
- 先生たちはそのリストを信じ、「この子たちは伸びるはず」と思って接するようになります。
- 数か月後、実際にその児童たちの成績やIQが本当に伸びていたという結果が出ました。
つまり、教師の期待が現実のパフォーマンスに影響を与えた=ピグマリオン効果の証明となったのです。
9,スノッブ効果
「スノッブ効果」というのは、他人と同じになるのを避けたくなる心理のことを言います。
要するに、「逆張り」と言われているやつです。
「みんながやっているからやりたくなくなる」「みんなが持っているから逆にいらない」
↑このような思考になるのは、この「スノッブ効果」のせいです。
もしそんな思考に陥ってしまったら、この効果を思い出してみましょう!
心理学って実はめちゃくちゃ面白い!
心理学って実は、専門用語ばかりの難しい学問ではないんですよ!
日常生活や人間関係、SNS、恋愛、買い物…など、私たちの行動のあらゆる場面に潜んでいて、実際に使用しています。
今回紹介した心理学のネタは、どれも「へぇ〜!」となるものや、人に話したくなるものを紹介しましたので、ぜひ友達や家族との会話、学校、職場…などで使ってみてくださいね!